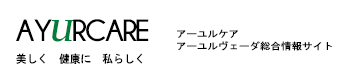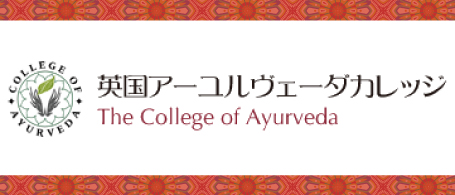タグ:食事
-
アーユルヴェーダにおける夕方の理想的な過ごし方
1日の疲れはその日のうちに取り除いて、明日も軽やかに活動したい!と思う方は多いのではないでしょうか。その思いを実現させるための重要なポイントは、夕方の過ごし方にあります。ここでは、アーユルヴェーダのディナチャリアにおけ…詳細を見る -
秋の不調を改善!ドーシャを整える秋の理想的な過ごし方とは
夏の暑さが和らぎ、冬に向かって気温が下がっていく秋。夏に蓄積したピッタが増大するだけでなく、急激な温度変化によってヴァータが増えはじめる季節です。 アーユルヴェーダの智慧を基に、日本の環境に合わせた生活を取り入れていく…詳細を見る -
アーユルヴェーダの食事法⑥食べ方にコツあり!健康的な食事のポイントとは
テレビを見ながら、仕事をしながら、食事をしていませんか?いくら良い材料と調理法で作った食事だとしても、食べることに集中していなければ、努力やこだわりは無駄になってしまいます。ここでは、しっかり消化を促進し、からだと心に良…詳細を見る -
アーユルヴェーダの食事法➀6つの味(ラサ)
疲れたり頭を使ったりすると、甘いものが食べたくなりますよね。これは、ヴァータが悪化しているため、体がバランスを整えようとしているためです。このように味には性質があり、消化の過程でドーシャに影響を与えています。あなたの体が…詳細を見る -
アーユルヴェーダの食事法 ②6つの性質(グナ)
食事の性質と心身に与える影響とは なんだか憂うつな気分だったり、体の乾燥がなかなか治らなかったり、そんなときみなさんはどうしますか?アーユルヴェーダには、食べ物にある6つの性質を活用して、体質や体調に適した食事法の智慧が…詳細を見る -
アーユルヴェーダの食事法 ④ラジャスな食事、タマスな食事
心が不安でいっぱいになったり、攻撃的になって言いすぎてしまったり、なにもやる気がでなかったり、誰でも経験する心の不調。もしかしたら、食事が原因かもしれません。今日あなたはなにを食べたいですか?心に浮かんだ食べ物を思い浮か…詳細を見る -
アーユルヴェーダの食事法③サットヴァな食事で心身ともに健康を維持しよう
心の状態も食べ物で変わる!サットヴァな食事で心を前向きにする方法 イライラしたり、やる気が出なかったりして悩んでいる方は多いのではないでしょうか。その原因は、食生活の乱れによるものかもしれません。アーユルヴェーダでは…詳細を見る -
アーユルヴェーダの食事法 ⑦旬のものを食べる「身土不二」
アーユルヴェーダから分かる旬のものを食べるメリットのご紹介 私たちは、技術の発展により、ほとんどの食材を1年中手に入れることができます。「旬の食材とは?」「取り入れるメリットとは?」と疑問に思う方も多いようです。実は、旬…詳細を見る -
症状によって異なる、頭痛の原因と適切な対処法は?
症状によって異なる、頭痛の正しい対処法と予防方法のご紹介 仕事や人間関係などのストレス、過労、不眠、PCの見すぎ、 雨天や季節の変わり目など、頭痛の原因はたくさんあります。大きな病気の前触れなどの頭痛ではなく、上記のよう…詳細を見る -
寒さの厳しい真冬、免疫力を高め健康で乗り越えるための過ごし方とは
アーユルヴェーダのリトゥチャリアにおける厳冬の過ごし方とは アーユルヴェーダでは、「理想的な一日の過ごし方」のことをディナチャリアと言い、「理想的な季節の過ごし方」をリトゥチャリアと言います。 ここでは、厳冬(冬至~)…詳細を見る